耳コピのやり方がわからない…
耳コピって何かメリットあるの?
 モンモン
モンモンそんな疑問にお答えします。
ポップスやジャズを演奏するなら耳コピをした方が良いという話、一度くらいは聞いたことがあるのではないでしょうか?
結論から言うと、耳コピはした方が良いです。
というより、耳コピができないプロに私は会ったことがありません。
それくらい、音楽(特にジャズ)をやる上で超重要な耳コピですが、やり方がわからなくて困っている人も多いです。
わたしも最初は耳コピが全然できず、「どうすればできるようになるんだろう?」と悩んでいた期間があります。
この記事を読めば、耳コピの正しいやり方・便利なツールなどがわかり、耳コピに対するアレルギーが無くなるはずです。
ぜひ最後までお読みください。
耳コピとは?ジャズやポップスをやる上で必要?
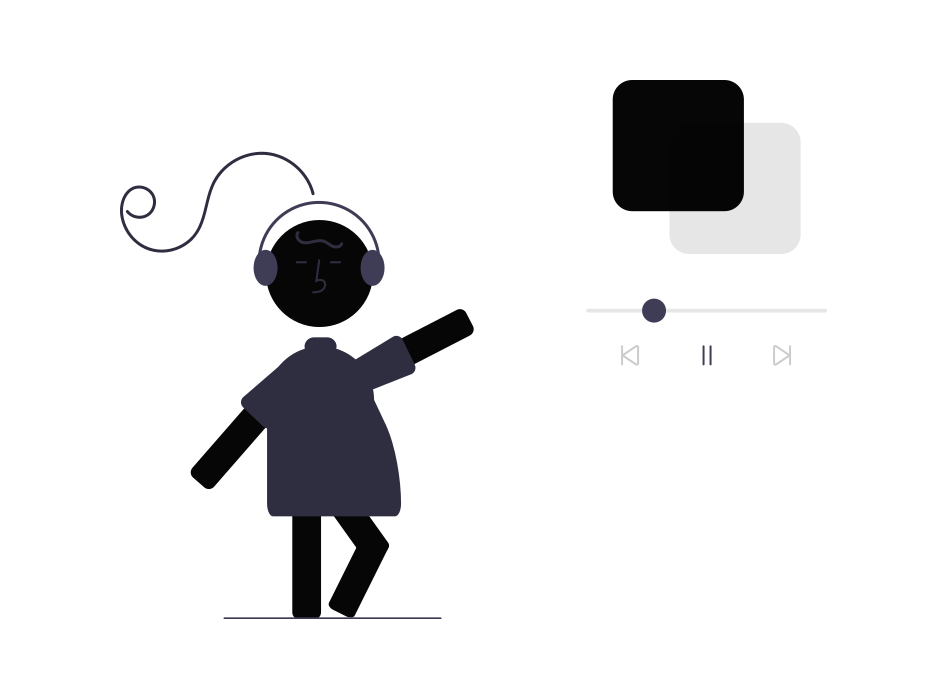
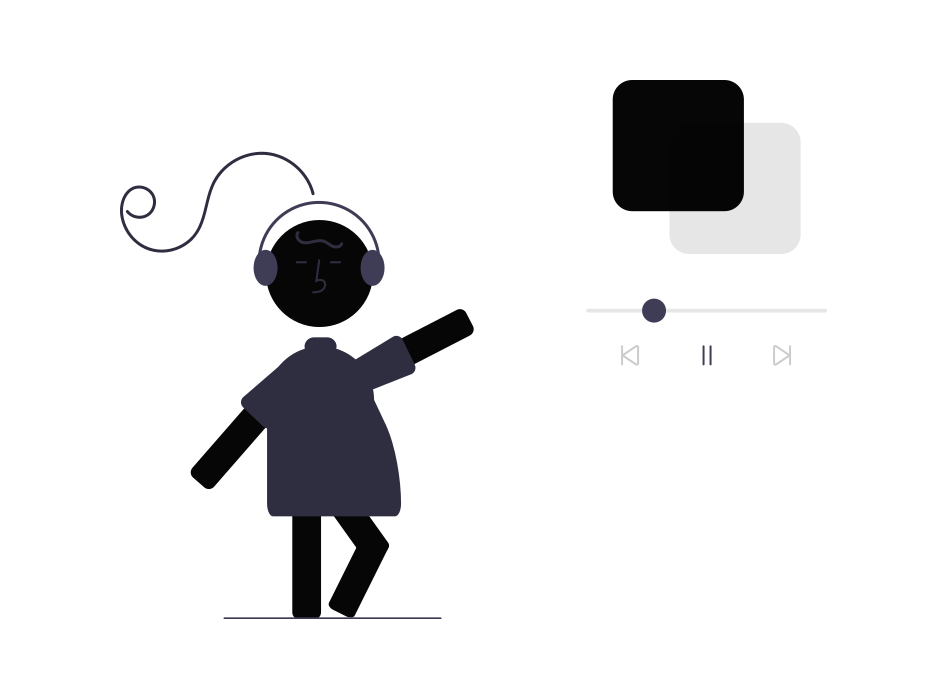
耳コピとは、その名のとおり「耳で聴こえた音をコピーする」ことです。
採譜(transcribe、トランスクライブ)とも言いますね。
さて、ピアノ経験者であれば、一度くらい流行りのポップスのピアノアレンジ譜面を購入したことがあるのでは?
あの譜面、どうやって作られているかというと、元の音源を耳コピしてピアノで弾きやすいように譜面を作成しているんです。
もし、耳コピができたら、あなたは自分の好きなミュージシャンの演奏を弾きたい放題…!!
さて、それでは、いったい耳コピはどのように行えばいいのでしょうか?



耳コピする時は、音源を何回も聞いて根気よく音を採ります。
「そのままかよ!」って思うかもしれませんが、実際その通りなので仕方ありません(やり方はこの後解説します)。
なお、多少の音楽理論も身に付けておくと、耳コピをさらに効率的に行えるようになります。
コード進行などを知っていると、次に来る音を予測しやすくなるからです。
コード・スケール・ボイシングの知識は。耳コピと同時並行で身につけたいですね。
極稀に、一回音源を聞いただけで完全再現する化け物級の人もいますが、それはかなり特殊の例なので気にしないでください(笑)



わたしはもちろん、普通はそんなことできません(多分)。
耳コピは「やったことのない人」からすると離れ業のように見えるかもしれません。
しかし、訓練次第で誰でもできるようになります。
耳コピに絶対音感は必要無い!初心者でもできます。
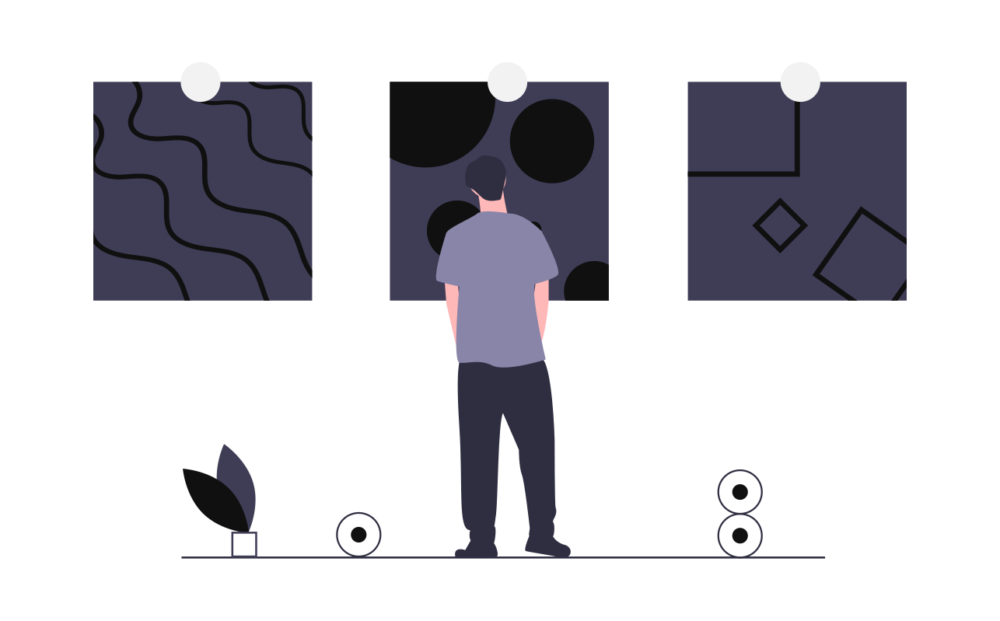
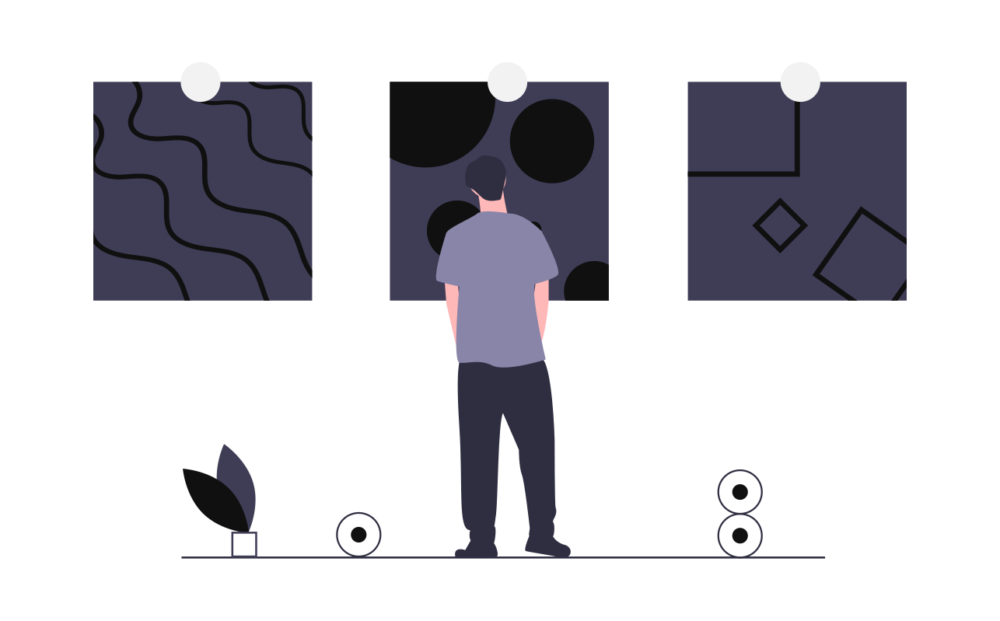
耳コピできる人はどうせ絶対音感があるんでしょ? 自分には絶対音感無いから無理だよ…



耳コピに絶対音感は不要です。
実際に絶対音感が無くても耳コピができる人はいくらでもいますし、自分もそのうちの一人です。



必要なのは相対音感で、誰でも習得できます。
- 絶対音感・・・基準が無くても、音がわかる
- 相対音感・・・どれか一音さえわかれば、それを基準に音を判別できる
本当の絶対音感があれば、譜面を見ただけで正しい音程で歌えるそうです。
絶対音感は先天的なものだったり、幼少期の訓練次第で身に付くものと言われています。
一方、相対音感は後天的に取得できる能力。
例えば、カラオケでキーを変換して歌うことってありますよね?
あれは、一定レベルの相対音感があるからこそできることなんです。
この相対音感があれば耳コピはできるので、絶対音感が無くても全く問題ありません。



因みに、私が初めて耳コピしたのは、大学ジャズ研に入ってからでした。
それまでは譜面を弾いた経験しかありませんでした。
ピアノ経験自体はそれまでに10年ほどありましたが、耳コピをしたことは無かったです。
そもそも自分で音を取るという概念すら、当時は持ち合わせていませんでした(笑)
ジャズ研時代にブルースの短いフレーズをコピーしたのが、耳コピの始まりだったと思います。
最初は耳コピの精度も、それはそれは酷いモノでした。
翌日改めて聞き直すと、全然違うということがザラにありましたし…(泣)



けど、頑張って耳コピを続けるうちに、ピアノの単音フレーズくらいは採れるようになってきました。
ある程度耳コピができるようになると、少し自信がつきます。
そして、今度は自分が演奏したい曲のリードシートを作ってみたくなりました。
スタンダード以外の曲は、自分でリードシートを作らないといけないことがよくあります。
しかし、リードシートを作るにはベース音やコードも聞き採る必要があります。
そこで、わたしは当時ジャズピアノを習っていたOB(セミプロ)に、コードの採り方を教わりました。
OB「じゃあ、ベース音採ってみてようか」
私「??…音源からベースが鳴ってませんよ、聞こえないです」
OB「いや、鳴ってるでしょ!」
私「(やばい、マジで聞こえない・・・)」



…当時は本当にこんなレベルでしたよ(泣)
この時学んだのは、”自分はピアノの音ばかり気を取られ、ベースやドラムをしっかり聞いていなかったんだ”ということです。
ピアノをやっていると、中音域~高音域は聞き取れても低音域は苦手という人も多いようです。
自分も苦手でした(今も?)。
それについては、「ピアニストの脳を科学する: 超絶技巧のメカニズム」でも書かれているので興味があれば読んでみてください。
こんな感じで、最初は全く耳コピはできませんでした。
しかし、できないのも当たり前です。
単純にそういう練習を今までやってこなかったからです。
言い換えれば、ちゃんと地道に継続すれば必ずできるようになります。
耳コピのメリット


耳コピをするメリットをわかりやすく解説します。
- 音感が良くなる
- リズム感が向上する
- 譜面に強くなる
- 音楽理論に強くなる
- 尊敬される(笑)
音感が良くなる
何度も音源を聞くので、自然と耳が良くなります。
細かいアーティキュレーションや音色などにも自然と意識が向くようになるので、音感は確実に良くなります。
リズム感が向上する
リズムも難解なものが出てくることがあり、どういう拍子なのかを考える必要があります。
その過程で、リズム感も良くなります。
譜面に強くなる
リードシート(メロディ・コードなどが書かれた譜面)を作る日が必ず来ます。
譜面を自分で作成するので、譜面の書き方を学ばざるを得なくなります。
その中で、譜面の読み方などをより深く理解できるようになります。
また、自分で譜面を作れれば、今まで買ってた楽譜代が浮くかもしれません(笑)
音楽理論に強くなる
耳コピをする際は、音楽理論を知っていると、候補の音をかなり絞り込めるので有利です。



耳コピの効率が上がるので、自ずと勉強するようになります。
音楽理論について学びたい人は、次の記事を参考にしてください。
正しい耳コピの方法
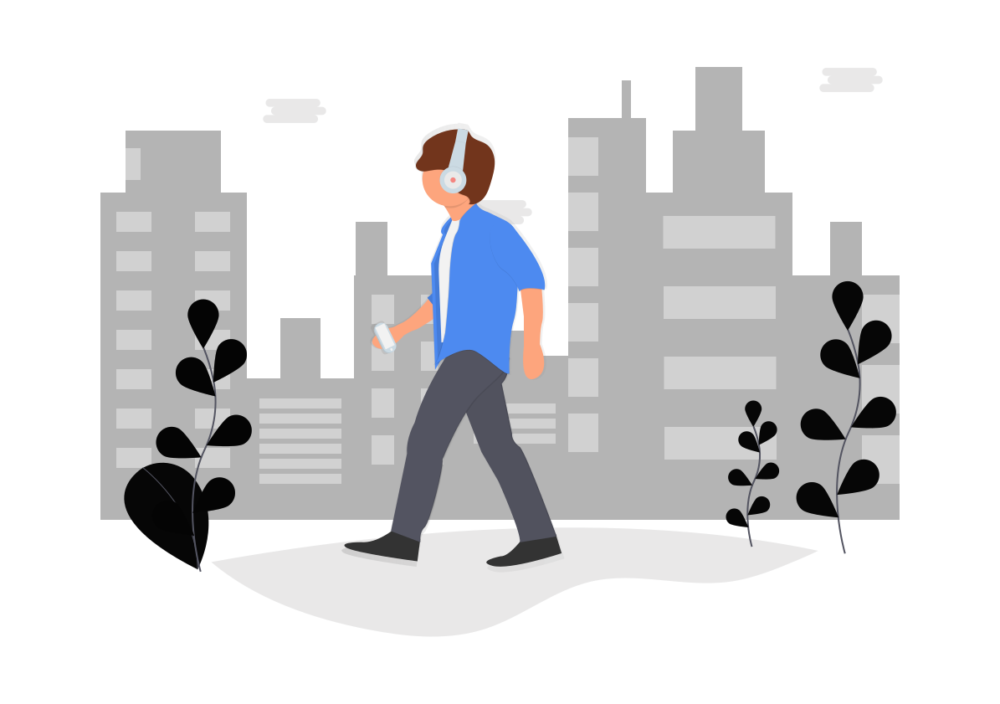
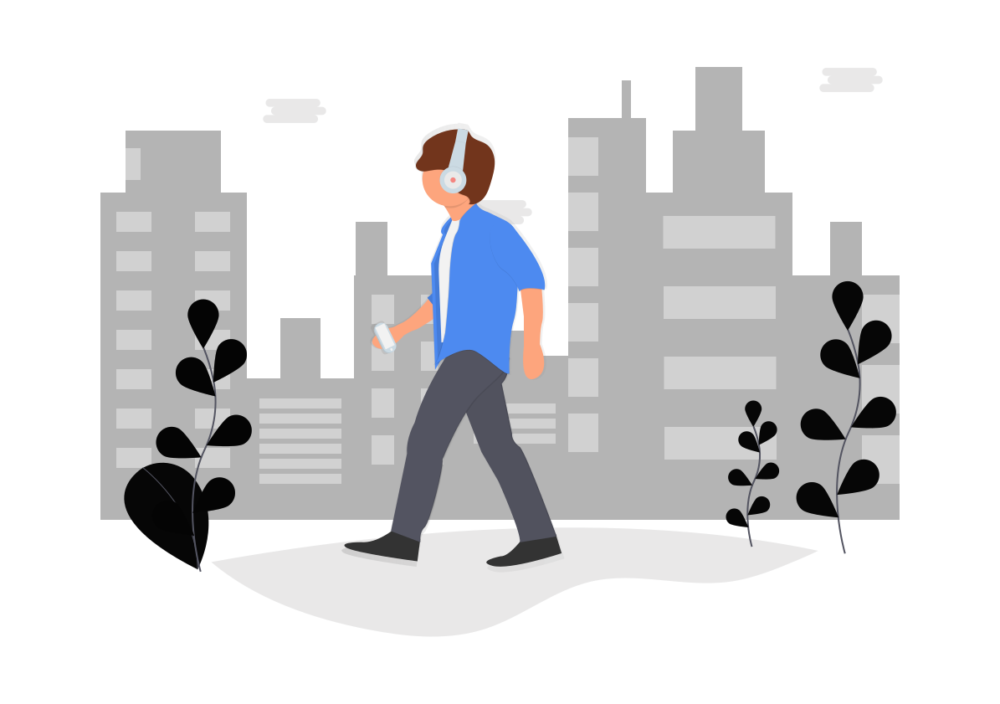
以下の順に行いましょう。
まずは一番簡単なメロディーから採りましょう。
メロディーはトップノートになっていることがほとんどです。
一番耳に残りやすいので、初めはここから攻略すると良いでしょう。
恐らく、最初はこれが一番大変だと思います。
特にジャズの場合、古い音源から耳コピすることもあります。
その場合、音が濁っていたり、音の輪郭がはっきりせず、採譜が難しいかもしれません。
どうしても音が採れない場合は一旦飛ばしましょう。
翌日もう一度聞くと、あっさりわかることがよくあります。 あと単純にベースが間違っている(音そのものの間違いやピッチが怪しい)こともあります(笑)
続いて、コード(内声)を採りましょう。
特に最優先で採るのは3度と7度の音です。
この2つがコードの特性を大きく左右するものだからです。
音程についてはこちらで学びましょう。
耳コピをする時の注意点は?
耳コピをする時に、よくある注意点を解説します。
完璧に採る必要は無い
クラシック経験者にあるあるですが、完璧主義は捨てましょう。



いつまで経っても進まないし、最初のうちは、ある程度妥協をした方が良いです。
日を改めて再び聞くとあっさり採れることもありますしね。
Done is better than perfect.
Facebookの創設者:マーク・ザッカーバーグ
完璧であることより、まず終わらせることが重要だ
音源を聞きながら耳コピすると間違えてしまうことも
結構やってしまいがちですが、これは強調しておきたいです。
ヘッドホンで耳コピしたい音源を聞きながら、ピアノで弾いて確認するのはおすすめしません(特にリードシート作成の場合)。
なぜなら、音源を流したままだと自分の音が間違っていることに気づかない可能性があるからです。



例えばコードを採っていたとして、本当はC△7だけど、Em7を弾いてもハマって聞こえることがあります。
それは、音源を聞きながらの場合、音源からベースが流れているのでC音が補完されるからです。
いざピアノだけで弾いて確認すると、「何か響き(印象)が違うな?」と感じたことがあるはず。
そういう時は、音源と実際に弾いている音を交互に確認することをおすすめします。
音源が間違った音を弾いていることもある
先に触れたように、音源が間違った音を弾いてしまっていることもあります。
「明らかにベースの音おかしいだろ!」みたいなこともあるんですよね(特に昔の音源)。
ここら辺は、音楽理論の知識や経験を積まないとわからないと思います。
はじめのうちは、あまり細かいところに固執しないようにしましょう。
どうしてもわからない場合の処方箋


どうしてもわからない場合はどうすれば良いですか?
対処法はつぎの通りです。
ネットで探す(無料)
誰しもが最初にやることだと思います(笑)
Googleで「transcription 」でググると出てくることがあります。
あとはYouTubeですかね。
自力で耳コピができるようになってからは、既存の譜面を参考にするのもありです(もしくは答え合わせで使用するなど)。
しかし、全くできない状態で既存の譜面に頼ると、いつまで経っても耳コピができるようになりませんよ。
採譜してもらう(有料)
どうしても急ぎで必要な場合はプロorセミプロに頼みましょう。
たとえば、ココナラでは譜面作成の依頼が可能です。
多くのクリエイターが登録しているので、比較検討すると良いでしょう。
- 耳コピで楽譜を作成致します(honoka515さん)
- キーボード・ピアノなどの耳コピ・譜面作成いたします(kots_ (scots)さん)
- ココナラで譜面作成を依頼する
今は利用しなくても、ココナラに登録しておくといつか使いたいときに便利ですよ。
耳コピ依頼のデメリットは
- コストがかかること
- 本当に耳コピできる能力があるかわからないこと
です。
耳コピの能力については、実績や評価コメントを参考にすれば良いでしょう。
また、トラブルにならないように、納期もしっかり確認しましょう。
耳コピに便利な機材・アプリなどのツール


耳コピをする上で役に立つものを紹介します。
ピアノ・キーボード
もし、管楽器の方が読んでいたらの話ですが、やはりキーボードがあった方が作業効率が良いですよ。
和音の確認は、やはり鍵盤の方がやりやすいです。
iPadやiPhoneを持っていれば、Garage Bandがあるはずなので、それを利用しても良いと思います。



iPhoneは小さくて使いにくいかもしれませんが…
CD-VT2(TASCAM) CDトレーナー
TASCAMのCD-VT2、もう10年くらい使ってます。
耳コピをする上でループ機能・VSA機能(音程を変えずに低速再生可能)は必須です。
そのような機能を有しているのがこの製品です。
耳コピの効率がまるで変わります。
私の場合、CDを買うことが多かったので(コレクター気質)、これを買いました。
というより、当時は選択肢がそれくらいしかありませんでした…。
「いまどきCDなんて買わないよ!」という人は後述のmimiCopyやAudipoでもいいと思います。
逆にCDを既に何百枚も持っている人は、CD-VT2も選択肢の一つにあってもいいかもしれません。
自分はボーカル用を購入しましたが、ギター用・ベース用どれでもいいと思います。
耳コピするためのアプリ、mimiCopy(おすすめ)



…ジャズ研時代に欲しかったです!]
今はアプリでいいものが色々ありますよね。
下手にハードを買うより良い場合が多いです。
これも上で紹介したCD-VT2のような機能はついていますし、ループ箇所も3つ指定できます(便利)。
使いやすく、安いアプリなのでmp3のようなファイルを用意できるのであれば、これだけで良いと思います。
NEW
最近では、Apple musicと連携できるAudipoもおすすめです。
Under Construction…
Looper for YouTube(おすすめ!)
YouTubeでは再生速度を変えることができます。
ピッチもそこまで変わらないので、テンポを落として練習したい時には便利ですね(あまりに再生速度を落とすと音が大きくゆがみますが・・・)
「ただ”ループ再生”ができないんだよな~」・・・と思ったあなた!
Looper for Youtubeを使用するとループ再生しながら、再生速度も変更できるので超便利です。
Google Chromeの拡張機能です。
chromeウェブストアで無料でダウンロードできます。
Tempo Advance(番外編:リズム練習)
耳コピとは直接関係ないアプリですが、便利なので紹介しておきます。
別サイトの記事ですが、詳しい紹介があったので、リンクを貼っておきますね。
このアプリは、ポリリズムの練習にとても役立ちます。
右手は3拍子、左手は4拍子で練習したいとき、両方の拍子を同時に慣らすことができ、リズム感向上にはもってこいの練習ができます。
市販されているメトロノームより安くて(500~600円くらい)高機能であり、スマホ一つで練習できるので重宝しています。
最後に
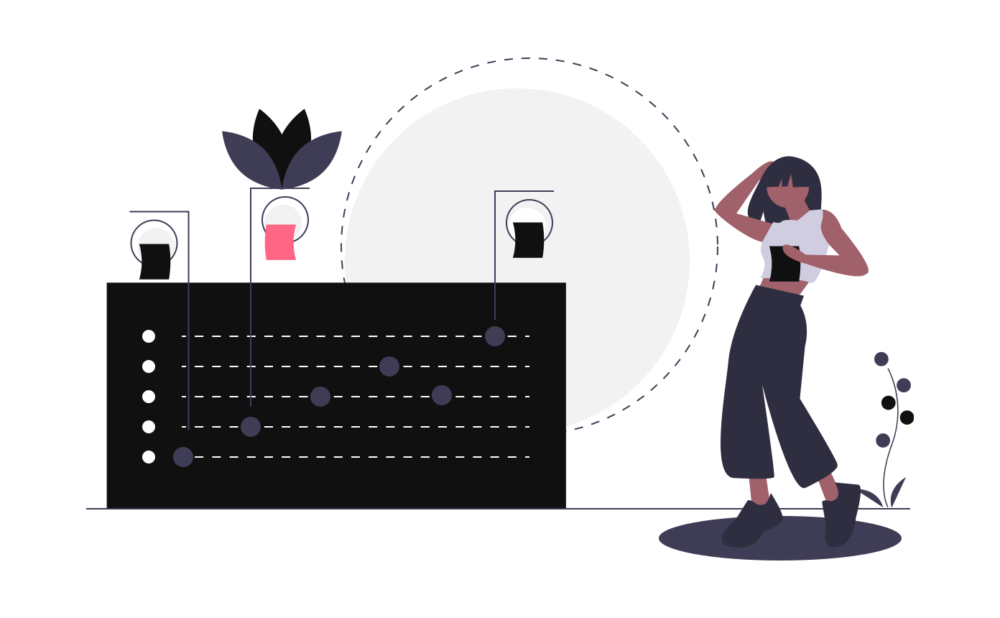
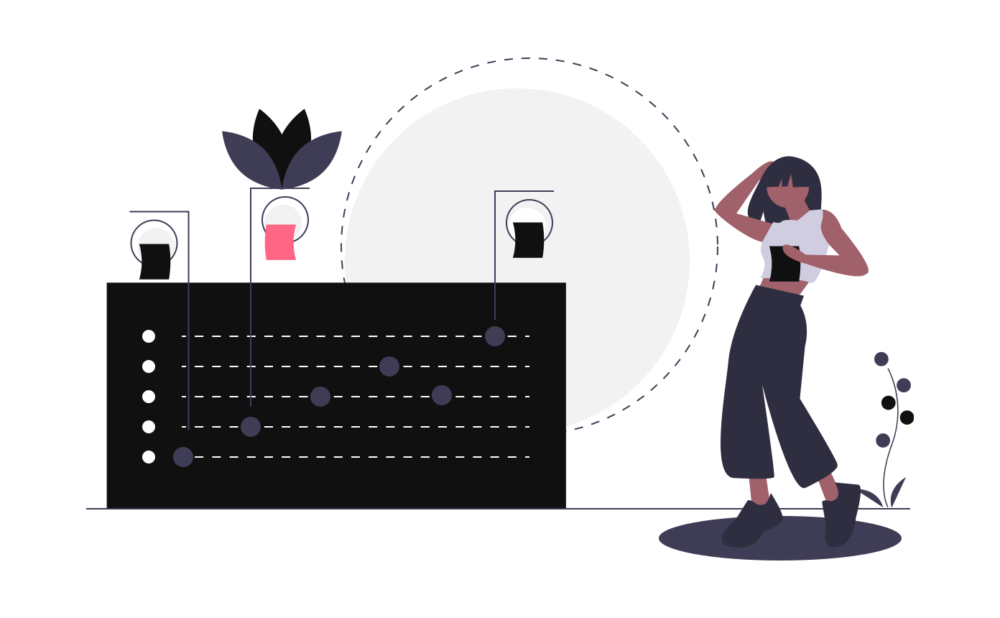
この記事では、耳コピの方法とメリットについて解説しました。



耳コピは最初は本当に大変です。
作業は全然進まないし、何回も心が折れると思いますが、皆が通る道です。
根気よく続ければ、最終的に和音もある程度採れるようになります。



ジャズを何倍も楽しめるように、少しずつでもいいのでトライして頑張りましょう!
以前、わたしが耳コピして採譜した動画も参考にしてください。
ちゃんと継続して耳コピをしていれば、これくらい音を採ることも可能ですよ!
耳コピについては、以下の記事も参考にしてください。

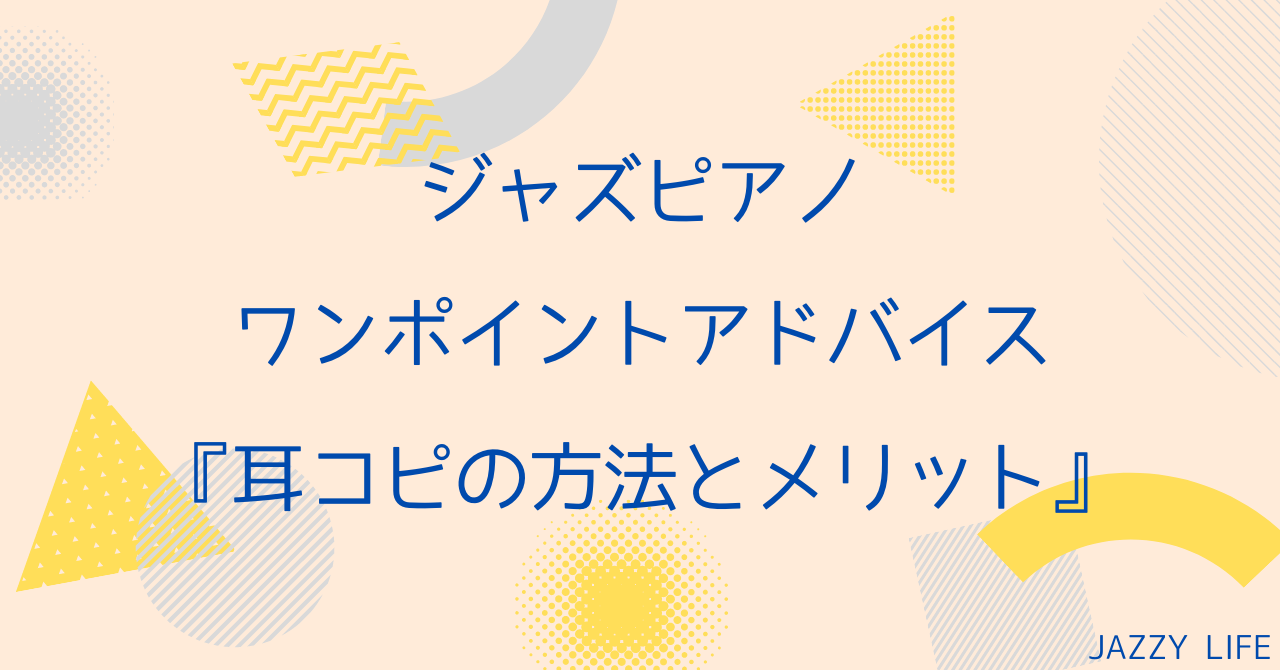
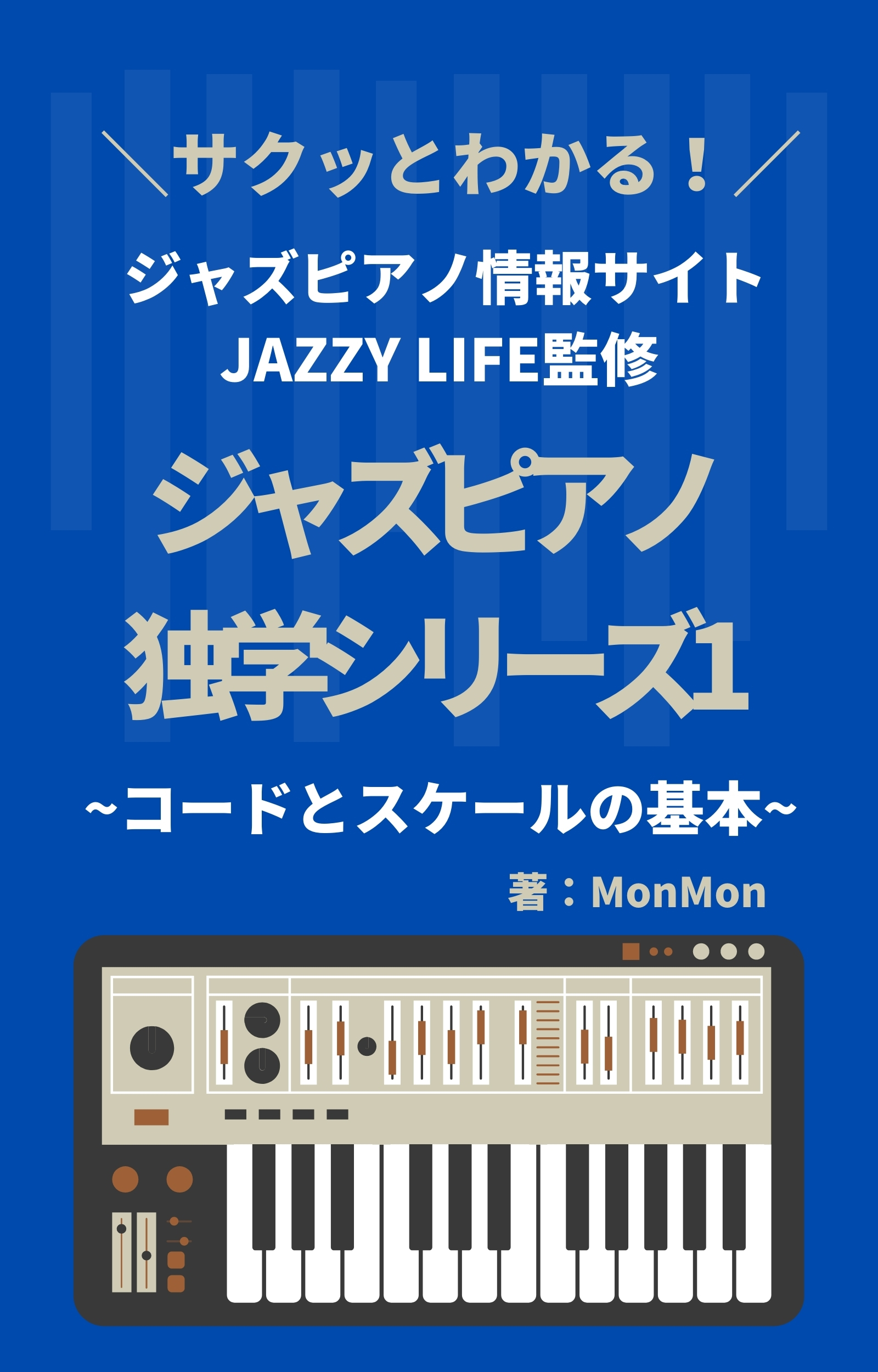



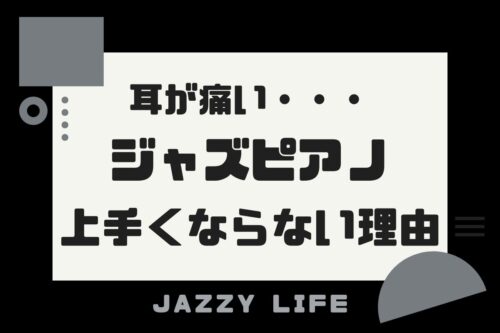
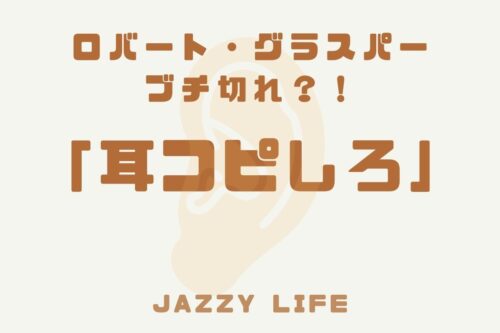


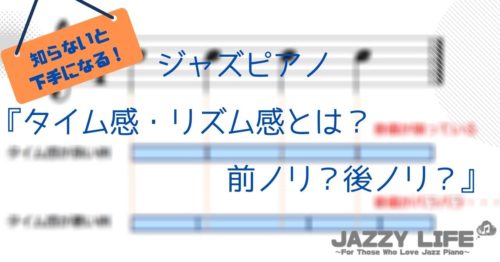
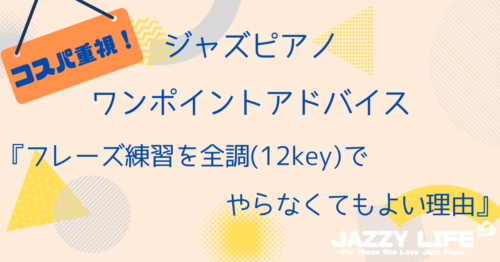
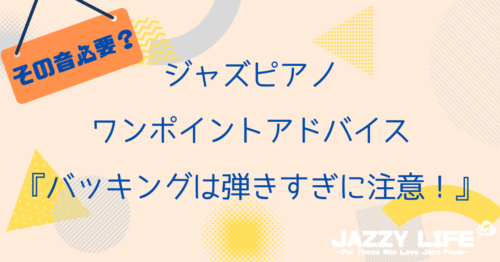
コメント